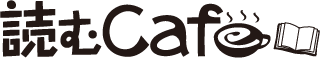芙美子の最愛の家族|林芙美子 「放浪記」を創る(18)
だぶんやぶんこ
約 3293
芙美子は建築中にも母を何度か案内している。
母も近くであり、何度も見に行き、出来上がるのを見守っていた。
ほぼ完成し入居が近づくと、母に、これからは絶対に側を離れないよう言った。
母も幸せそうにうなづいた。
この時、鹿児島から、姉の子、姪二人、福江(1925-2018)と妹が来た。
東京の学校で勉強するようにと呼んだのだ。
昔、芙美子が鹿児島の祖母の家に世話になった頃、顔を見合わせたことのある異父姉の娘だ。
母、キクは育てることはなかったが、祖母が福原家に嫁に出し、生まれたのが、林福江と妹。
連絡を取り合っていたが、母のためにも来て欲しいと頼んだ。
こうして、芙美子と緑敏、母と福江ら姪二人との同居暮らしとなる。
芙美子の家族とは、五人のことだ。
故郷となる我が家が出来たこと。
愛する家族を持ったことに、しばらくは十分満足だった。
だが、何か足りない。
幸せな家族、夫と子供に囲まれた楽しい我が家が、目に浮かび、憧れていく。
子供が欲しい、子供が出来ればいつ死んでもいい、でも家族が出来るまでは死ねないと頭が壊れそうになる。
芙美子と夫、緑敏の子が一番だが、もう望めない。
できれば、芙美子と同じような境遇の女の子が欲しくて欲しくて、居ても立ってもいられなくなる。
今までも養女を願ったことはあったがうまくいかなかった。
愛の結晶として生まれたけれど、父親が言えず、母親自力では育てられない女の子を育て、幸せにしたかった。
芙美子の苦労を経験させることなく、幼い時から幸せにするのだ。
親知らず子知らずで、子供を預かり養子にしようと探し始めた。
そして知り合いの産院から親が育てられない事情のある子が産まれると聞く。
子の親のことは何も聞かなかった。
それでも、近くの産院であり、ここで子を生む人のことはよく知っており、だいたいのことはわかっていた。
大急ぎで産院に駆け付け、生まれたての赤ちゃんを引き取る。
1943年12月、夫、緑敏の留守中、男の子を得意げに貰ってきた。
緑敏は家に帰って、たった今生まれたような男の子が家に居るのを知り驚いた。
芙美子はもう赤ちゃんに夢中で付ききりだった。
以前から子どもを育てたいと、言っていたけれど、現実となったのだ。
満面に喜びをたたえ「我が子よ。私の子よ」と何度も何度も取りつかれたように言う芙美子だ。
「訳が分からない、直ぐには納得できないよ」とぼやきながらも子を見て緑敏も微笑んだ。
緑敏は、芙美子の行動のほとんどを掴んでいる。
共に暮らして18年、多くの顔を持つ複雑な芙美子だが、作家ではない妻として見ると、単純だ。
友人関係も人脈も分かっている。
どこの産院からどのような経路で子を得たか、想像はつく。
芙美子は、自宅の半分を緑敏名義とした。
伴侶として、認め感謝しているのだ。
その溢れるほどの愛を緑敏は、十分感じている。
芙美子の幸せは、自分の幸せ、この赤ちゃんを共に幸せにするのも悪くないと思う。
だが、これほど小さい赤ん坊を育てられるのか心配だ。
夫、緑敏の表情の変化を芙美子は見逃さない。
緑敏は、この子を受け入れたと感じた。
そして「この瞬間をどんなに待ち続けてきたか。素晴らしい家族になった」と落ち着いて話す。
緑敏はうなづいた。
最後の仕上げだ。
緑敏に「家族を作りたい。入籍して欲しい」と頼んだ。
緑敏は、いつものように、うなづいた。
こうして、夫、緑敏と養子、泰を芙美子の戸籍に入れ、名実ともに、林芙美子の家族が出来た。
1944年3月、すべてが芙美子の夢の通りに叶った。
芙美子は、一家が出来、いつ死んでも良いと思う。
しかし、まだ戦時中、乳飲み子をかかえ、育てるのは大変な苦労だった。
緑敏はもう少し母乳で育ててから預かれば楽なのにと言った。
素知らぬ顔で「私の子だもの。私が生まれたときから育てるの」と言い放つ。
誰が何を言おうと、全く苦にならなかった。
それほど、泰は可愛かった。
ただ戦況は悪化し、東京は空襲が続き、生活物資の供給もままならない戦況となった。
泰のために周囲は疎開を勧めた。
自宅が好きで離れたくなかった芙美子だが、納得した。
4月、戦争との関わりがいやで、どう表現すべきか、行き詰っていたこともあり、環境を変えて自分を、作家としてすべきことを見つめ直すのもいいかと、緑敏の勧めに応じた。
母と泰そしてお手伝いさんと四人で、夫の故郷、長野に疎開する。
同居していた福江姉妹は、実家、鹿児島に戻る。
戦時中でも出版等々、芙美子の仕事の本拠は東京にあり打ち合わせは必要だった。そこで、緑敏は、東京と長野を行ったり来たりすると、家に残る。
まず、信州上林温泉の旅館「塵表閣」に移り、続いて角間温泉を疎開先とする。
戦時下の不自由な生活だが、自然の中でのんびりした田舎暮らしが始まる。
じっとしていられない性格で、田畑を耕し、種を植え育て、そして、収穫する農作業に嬉々として取り組む。
農業で生きる喜びを身体いっぱい感じ、現地の人たちと親しくなる。
まもなく来た冬の寒さと、外に出られない退屈さには、耐えられなくなる。
尾道を出て以来の初めての長い休暇だからゆっくり休みなさいと言われても、いらいらが募る。
時には、東京に戻りたいと、周囲に当たり散らした。
それでも、アルプスの山々に包み込まれて、肉体的には素晴らしい充電期間となった。
閉ざされた冬の楽しみを見つけ、満面の笑顔が戻る。
村の子供たちのために「童話」を書き、語るのに没頭したのだ。
子供たちの笑い声に、生きている自分、役に立っている自分を感じ、最高だった。
天真爛漫な少女がそのまま大人になったかのような芙美子は、子どもの目線で話すのが自然に出来、それこそが芙美子だと芙美子自身が酔い浸り、素晴らしく饒舌になる。
芙美子の言葉が、心に響き、そこから生まれる子供達の怒り・悲しみ・不安の表情をじっと見つめる。
その顔に合わせ、話を明るく変えたりと、自由自在に話をすすめる。
すると、子どもたちの顔が、意図した顔に変わる。
そんな顔を見るのは作家冥利に尽きる幸せだ。
毎日子供達を驚かせようと、奇想天外な話を作る。
子供達は動物になったり、空を飛んだり、船に乗って見知らぬ土地を冒険する。
そして、はしゃぎ廻って目を輝かす。
泰に残すんだと思うと、一層張り切り、童話を考えるのが最高の楽しみとなった。
泰の幼い顔を見ていると、次々と、童話が湧きだして来る。
「目指していた作家とは、童話作家だったんだ」としみじみ思う。
「作家になって良かった。こんな幸せはない」と、癒されるやすらぎを感じ、涙が溢れる。
あれがないこれもないと不平たらたらの生活だけれど、母と泰、時々緑敏の暮らしは充実していた。
それでも南方戦線を見た時の惨状を忘れることはできない。
日本兵の疲弊した姿、戦況の不利な状況を知って以来、どう表現すべきか、苦悩の中にもいた。
作家、芙美子が問われていると、覚悟を決めたが、模索する日々だった。
ついに、恐れていた通り、1945年8月、日本は全面降伏し、戦争が終わる。
我が家は、絶え間ない空襲にあったが、奇跡的に無事だった。
1年7ヶ月を過ごした疎開先から戻る日が来る。
名残惜しくなっていたが、仕事が待っている。