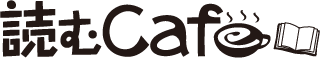直虎と西郷正友|井伊直虎を彩る強い女人達。(4)
だぶんやぶんこ
約 7709
直虎が、直政と家康ゆかりの姫との結婚を願い、取次ぎを頼んだ西郷正友。
養子、直政を徳川家康に託すと決めた時、その根回しをして、対面の場を作ったのが西郷正友であり、以後、井伊家と家康を繋ぐ役目を担った。
西郷正友は、後の2代将軍、秀忠の母、家康側室、西郷の局の義弟(西郷の局と死別した先夫の弟)だ。
瀬名姫は、正室であり、嫡男を生みながら、家康に殺された。
西郷の局は、側室だが、嫡男の母となる女人だ。
この頃、秀忠は、家康の3男として生まれたばかりだった。
だが、家康は、家康側近の周知のことであり、次男、秀康をやむなく認めたが、嫌っており、心中は認めていない。
そのため、家康は、秀忠を嫡男、信康に継ぐ子、後継にもふさわしいと考えた。
側近らもそのように思う。
直虎は、嫡男の母、瀬名姫から、新たに嫡男の母となる可能性の大な西郷の局に、井伊家存続・飛躍の願いを託したのだ。
家康に仕える、西郷正友(1552-1604)。
菅沼定盈(1542-1604)と共に遠江の諸将を家康方とするために働く叔父(父の弟)西郷清員(1533-1595)が、遠江の諸将と対面する時、正友も共に会う。
西郷家当主の兄に従っていた正友だったが、1571年、兄が戦死し、当主が、清員の子となり、清員に従うよう命じられたからだ。
そこで、井伊家との繋がりができる。
秀忠の生母、西郷の局(1552-1589)は、家康に仕える前、1567年、西郷家(嫡流は松平一門、大草(岡崎)松平家)当主、義勝に嫁いだ。
義勝の先妻が亡くなり、残された遺児を育てる為の再婚でもあった。
西郷の局は、戸惑いながら赤子の面倒を見た。
西郷の局にも娘と勝忠が生まれ、日々の暮らしになれた、1571年、夫は、家康に命じられて武田勢と戦い、戦死してしまう。
悲しみの中で、子たちを抱きしめ、西郷家を引き継ぎ守ると決意する。
母として西郷家を担うのだと責任感で震えた。
だが、家康は幼すぎると嫡男、繁勝が後継になることを、認めなかった。
それなら、義勝の弟、正友を中継ぎとし、義勝の子が成長後、当主にしたいと願う。
懸命に戦い、討たれた夫の遺志であり実現したかった。
ところが、家康は義勝のいとこ、家員(清員の嫡男)に西郷家を継がせると厳命した。
戦国の世、当主は家中を率い戦うべきであり幼い当主では家中を率いることは出来ないと言われ、了解せざるを得なかった。
れでも西郷家嫡流は正友の父、元正から義勝に引き継がれており、血筋を重視すれば、義弟、正友が継ぐべきと思う。
家康の命令で戦い、義父、元正も家康のために、戦死している。
清員は、元正の弟だ。嫡流ではない、弟の家系に家督を取られのだと悔しい。
家中を率いる力もある義勝の弟、正友を当主にしたい思いを引きずった。
だが、家康は、元正の弟、清員に後見を命じて、清員の子、家員に継がせた。
家員と西郷の局の娘を結婚させ、後継者としたことで、西郷の局の意向を重んじた。
西郷の局は喜ばなかったが。
家康が、清員を気に入っていたゆえ、決めたことであり、覆せない。
西郷家は松平宗家(1566年より徳川家)に従っていた。
松平広忠が義元に従うと西郷家も従い、1562年、家康が今川氏真と決別すると同じように西郷家も今川家から離れ家康に従った。
その際、元正の弟、清員が家康に忠誠心を示す人質となり岡崎城に入った。
清員は家康に仕え戦い力を発揮した。
家康は、戦功を褒め、伯母(父の姉)碓井姫の夫、酒井忠次の妹との結婚を決めた。
家康から「(清員は)身内になった」と祝され、清員は西郷家筆頭と見なされていく。
その後、嫡男、家員が、西郷家を継ぐよう命じられた。当然だった。
西郷の局は、清員は分家に過ぎないと、納得しなかったが。
娘婿ではあるが、家員15歳が当主となり、西郷の局は、その庇護下で義勝の遺児を育てることになった。
それでも、嫡流の座を奪われ心が晴れない日々が続く。
遺児の将来も心配だが、家員と正友のぎくしゃくした関係を目の前にし、心痛める。
正友は18歳、家康の裁定に納得できず家員の配下に置かれるのが我慢できなかった。
それでも、清員・家員と共に、家康の命令に従い働き戦う。
家康は今川義元亡き後の1562年、信長と同盟を結び遠江の国人衆を味方にしつつ、配下とし今川領に侵攻していく。
その時、遠江に近い東三河の有力国人、菅沼定盈に清員と共に、遠江井伊谷(静岡県浜松市)の諸将を家康の味方にするよう調略・説得を命じた。
菅沼定盈は、清員の母の弟の子、いとこだった。
西郷元正・清員の母は、菅沼定盈の父、定村の姉。
菅沼定村も今川氏に属したが家康に従い今川氏から離れ、定盈を人質に差し出した。
定盈の母は、深溝松平家、忠定の娘。
深溝松平家は、家康の親戚衆、松平一門だ。
家康の元、定盈はよく戦い認められ松平一門、長沢松平家、政忠の娘との結婚が決まる。
清員と定盈は、よく似た経緯で人質となっている。
両家の家格も似ており、岡崎城下の屋敷も近く、気安く付き合った。
家康も好ましく思い、仲の良い二人に同じ役目を与え、競わせた。
定盈は、まず、後に家康が井伊谷三人衆(近藤康用、菅沼忠久、鈴木重時)とする中の一人、菅沼忠久の調略を命じられた。
遠江引佐郡都田(浜松市北区都田)の有力国人、菅沼忠久は、一族であり、近しく、縁があったからだ。
忠久が家康方に付くことで、周辺の遠江の国人衆が、一挙に味方になると、定盈と清員は必死で取り組んだ。
時間をかけ、煮詰め、調略を成功させ、1568年、忠久は家康に臣従を誓った。
以後、忠久が井伊谷三人衆の他の二人、近藤康用、鈴木重時を取り込み、周辺の国人衆にも働きかけ急速に家康に従う国人衆を増やした。
家康が任じた井伊谷三人衆は、直虎の重臣でもあり、彼らは、直虎にも積極的に働き掛けた。
直虎は、家康への臣従を以前から決めており、井伊家が井伊谷の盟主としての地位を安堵されるとの確約を得ると、家康に従うことに同意した。
水面下で遠江衆の調略が進んでおり、今川氏攻略の道筋が出来ていることがよくわかっていたからだ。
筆頭家老、小野氏の裏切りに乗じて、今川配下から一転、家康勢の一翼を担い、今川勢と戦うことになる。
定盈と清員との2人は、今川勢を追い払った後も、遠江の国人衆を完璧に家康配下とするために働く。
1571年、正友の兄、義勝が戦死、西郷家当主は、父の弟の系統に移った。
西郷家当主は、清員の家系となり、配下となった正友は、清員に従い遠江の国人衆と
家康を取り次ぐ役目を得る。直虎と会う機会が出来たのだ。
直虎は、瀬名姫を頼りとし家康の配下となったつもりでいた。
そのため、正友に特別な関心はなかった。
それでも影がありながらも取次の役目を懸命に果たす真面目な姿を目に留めた。
その後、直虎と直政主従は武田勢に追われ、浜松城に逃げ込むことになってしまった。浜松城内での直虎母子の暮らしの面倒を見るよう命じられたのが、西郷正友。
正友は細かい心配りで直虎たちが日々快適に過ごせるよう誠意を尽くした。
戦時下の重苦しさの中で、落人の身ながらも落ち着いた日々を過ごすことができ、正友への親しさを増した。
この繋がりで、1575年の直政と家康の初お目見えのおぜん立てに、正友が頑張り、直政は家康に召し抱えられた。
この後、正友の義姉、西郷の局が家康の側室となる。
直虎は、西郷の局と正友の関係に、興味を持つ。
瀬名姫を思うと切ないが、家康が側室を持つのはやむを得ないと思う。
その女人が、正友の義姉だと知り、因縁を感じる。
1579年5月2日、西郷の局が家康三男、秀忠を生む。
家康は、元気な赤子であると確認すると嬉しそうに、次の行動に移る。
9月19日、瀬名姫を殺し、続いて10月5日、嫡男、信康も殺したのだ。
家康には、三人の男子がいた。
嫡男、信康、母は瀬名姫
次男、秀康、母は小督の局
三男、秀忠、母は西郷の局。
家康は次男、秀康の母の男性関係を疑い信用せず母子共々嫌い後継者とする気はない。
嫡男、信康は、岡崎衆をまとめ家康に対抗する恐れがあった。その為殺したのだが。
この時点で、家康が誕生を祝した秀忠が、嫡男の第一候補だった。
その生母の義弟、秀忠の叔父となったのが、西郷正友だ。
直虎は、瀬名姫が紡いだ縁と感じた。
かって西郷の局は、夫を亡くし、家康の仕打ちを恨みながら、残された遺児を育てる日々だった。
そこに、家康から側室に迎えたいとの知らせが入った。
半信半疑で理解に苦しんだ。
西郷の局の願いをことごとくつぶされ、好かれることなど考えてもいなかったのだが、現実のことだった。
西郷の局は、たくましく知性も備えていた。
前夫の子達と正友の将来の為に役に立つ吉報であり、女人として高い評価を受けた証だと、頭を切り替えた。
家康からの命令をありがたいことだと、謹んで受け、浜松城に入った。
家康の愛妾となり、秀忠が生まれた。
家康の認める子の母となると、周囲の態度が大きく変わる。
皆が、西郷の局に一目置くようになり、発言力も増していく。
ここで意を決し、家康の子の母として、正友及び義勝の遺児への温かい配慮を求める。
家康も承知し、弟、西郷清員の系統が嫡流と見なす流れは変わらないが、西郷家を家康の子の母の実家だと認め、引き立てた。
ここから西郷正友が、重く扱われ、西郷清員と同格になっていき、別家を起こすことになるはずだった。
ただ、家康は、西郷家嫡流は清員の系統と決めており、相応の家格の付家老とし、家康直臣から外すつもりだった。
ここから、井伊家の重臣となる道ができていく。
家康は、我が子の生母の実家が力を持つ事を嫌い、最低限の面子を保たせる程度の優遇しかしないが、正友には、十分だった。
直虎は、瀬名姫が死と引き換えに西郷の局とのめぐり逢いを創ってくれたと震える。
正友を直虎の元に送ったのは瀬名姫だったのだと、信じられないほど大きな力を感じる。
国人衆の一つにしか過ぎない井伊氏が、家康の譜代一になる大きな要因の一つが瀬名姫から続く西郷の局との縁から生まれたのだ。
井伊家と家康・瀬名姫・西郷の局との因縁が絡み合い井伊家は甦る。
直虎は、直政が家康を主君と決め頭角を現してくると、瀬名姫との縁を深め、直政の後ろ盾になってくれるよう願うつもりだった。
だが、家康と瀬名姫の不仲は誰の目にも明らかになっており、他の家康に仕える女人との関係を良好に保つことも考えなくてはと思い始めた。
家康と良好な関係を築くには、直政の活躍が一番だが、家康の奥との結びつきも重要なことだった。
そこで西郷の局が側室になった経緯を知り、家康が子を望んでいるとひしひし感じた。
瀬名姫はまだ生きていたが、西郷の局にかける家康の思いを知り、先を見越し、西郷正友は役に立つと、直虎は、家康との取次役となるよう願った。
こうして、正友と、度々、会うようになった頃、瀬名姫は役目を果たしたかのように亡くなった。
瀬名姫の死を悼み家康に複雑な思いを持ちつつも、西郷の局・正友と結ぶ道を作り残して瀬名姫は逝ったのだと不思議な力を感じる。
感動し冥福を祈った。
正友は、直虎に引き立てられたことを感謝し、直政の優秀さに心打たれ全身全霊で井伊家の為に尽くした。
直虎も、その様子を見て、直政にとって良き家臣になると、改めて瀬名姫に感謝する。
家康家臣としては立場をなくし、やる気が失せていた正友が、直虎に推され直政との巡り合いで力が満ちた。
主君は、直政しかいないと臣従を誓う。
家康は1582年、直政の結婚に合わせて正友を直政の付け家老とする。
井伊家重臣とし日の当たる処に出したのだ。
ここで、正友は西郷家別家を興す。
西郷の局は、秀忠の側近としたかったが、了解するしかなかった。
家康は、西郷正友を秀忠近習とすることを認めなかった。
正友の野心を感じ、徳川家臣としての価値はないとみなした。
それでも、それ故に、直政にとっては、快挙として得た家臣だ。
家康嫡男の母になるかもしれない側室、西郷の局の義弟が付け家老となるのだから。
直政は、家康の配慮であり認められた証だと、重々しく受け止めた。
家康の期待に応えなくてはならないと、高鳴る思いで一直線に戦い続ける。
家康は、1568年末、武田信玄と同盟を結び共に駿河に侵攻する。
今川領の分割を決め、遠江(静岡県西部)は家康領となる。
そして、氏真を追い払うが、遠江は、長く今川領だったため、今川氏の支配力が浸透していた。
氏真が家督を継ぎ情勢は不安定になっていたが、今川氏を無残に追い詰めた家康が支配者として乗り込むのは、今川氏への愛着を忘れない国人衆には不本意なことだった。
敗者に対しての同情もあり、独立性が強い遠江国人衆を、円滑に支配下に置くために大義名分が必要だった。
それには、瀬名姫の名が、価値を持つ。
義元の娘として嫁ぎ、今川氏を引き継ぐ正当な権利を持つのが瀬名姫であり、その夫、家康は、今川家を引き継ぐ大義名分を持つとした。
瀬名姫の夫であることを大義名分として、遠江支配の柱とし、今川旧臣・遠江国人衆をうまく活用し慎重に支配下にしていく。
氏真は1569年、徳川勢・武田勢に追い詰められ、今川氏本拠、駿府城を捨て、遠江掛川城に落ち延びた。
今川氏を再興すると意気盛んに檄を飛ばしたが、配下だった国人衆は集まらない。
掛川城に籠城することしか出来なかったが、ひたすら閉じこもった。
こうして、掛川城を守り抜き、半年の籠城後、家康と和睦、開城する。
条件は氏真を家臣団と共に妻の実家、北条氏康の元に安全に送り届けることだった。
家康は了解し、送り届け、北条家に落ち着いた氏真は、北条勢を頼りとし、駿府城に返り咲く為に、駿河侵攻を企て武田勢と戦う。
手勢は少なく武田勢は強く、状況は好転しない。
むなしい思いが募るばかりだった。
そこに、追い打ちをかけるように、頼みの義父、北条氏康が1571年、亡くなる。
後継、氏政は、武田勢と戦っても勝利の目途はなく、益もないと見極め、信玄と再び同盟を結と決めた。
信玄との友好関係を復活させ、駿府への侵攻をやめたのだ。
ここで、駿府奪還を目指し武田氏と戦い続けたい氏真は、北条氏にとって迷惑な存在となってしまった。
氏真は、頭を抱えた。
そして、信玄の支配する駿府に戻ることは不可能と悔しく情けなく、悟る。
進退窮まった。
そこに、家康から、名誉ある待遇で迎えるという申し出があった。
1572年の初め、家康の申し出を受けることに決める。
憎んでいた家康に庇護されることを選んだのだ。
家康は、今川氏宗家嫡流、氏真を取り込み、今川氏を継承する大義名分を得たと、喜んだ。
遠江支配は、楽になり、国人衆をまとめ、円滑に支配下に置くことができる。
すぐに、氏真を武田氏追討の先頭に立たせる。
1575年、諏訪原城(牧野城)(静岡県島田市)を武田勢から奪うと、翌年、氏真を城主に据えた。
武田勢を追い詰め追い払う侵攻は順調で、名実ともに今川領を引き継ぐ体制が出来た。
氏真も、家康の力を借りるのは心外だが、駿府を取り戻す第一歩を踏み出したと驚喜し、家康の先兵となり戦う。
諏訪原城(牧野城)主となると、次に目指すのは駿府城主であり、今川氏は蘇るはずだった。
駿府の支配者となる前段階の諏訪原城(牧野城)主だと、思うままに統治し、家康の指示には従わない。
家康は怒り1577年には、城を取り上げ、浜松城近くに住まいを与え、反家康的な行動を取らないよう監視する。
氏真は正当な今川家後継であり、庇護する家康は正統な後継者だとの大義名分を守りたく、まだまだ価値ある人物だと、相応に大切にする。
それでも、権限を削ぐべく隠居を強制し、氏真は出家した。
氏真を完全に手中に置いた。
ここで、岡崎衆を率い独自の勢力を持とうとしている妻、瀬名姫と嫡男、信康に頭を痛めていた家康は、鉄槌を下す。
1579年、瀬名姫・信康を用が済んだとばかりに殺した。
以後、じっくりと慎重に武田氏を追い詰め滅亡させ、1582年には、信長から駿河を与えられる。
この間、遠江勢はよく戦った。
直政・西郷正友らの見事な働きを、家康は褒めた。
この間、正友も自らの幸運に驚く。
西郷の局が家康の子2人、秀忠と松平忠吉を生んだのだ。
義弟として権威が増し家康近辺の重臣から一目置かれ、井伊家と家康との取次に力を発揮していく。
そんな正友を見込み、直虎は、直政の結婚への取次を頼んだのだ。